こんな受験生におすすめ
- 共通テストと私大どちらにも対応したい人
- 参考書が多すぎて選べない人
- 山川だけでは理解が不安な人
- MARCHや上位私大を狙う人
日本史は「何をやるか」より「何をやらないか」が重要な科目です。参考書は種類が多く、山川・講義本・一問一答・資料集・問題集…と揃えようとすれば終わりがありません。でも実際に必要なのは「目的に沿った流れ」と「選ぶ基準」です。ここでは、共通テストからMARCH・私大まで対応できる、分かりやすく確実な参考書日本史の攻略法を紹介します。
この記事の目次
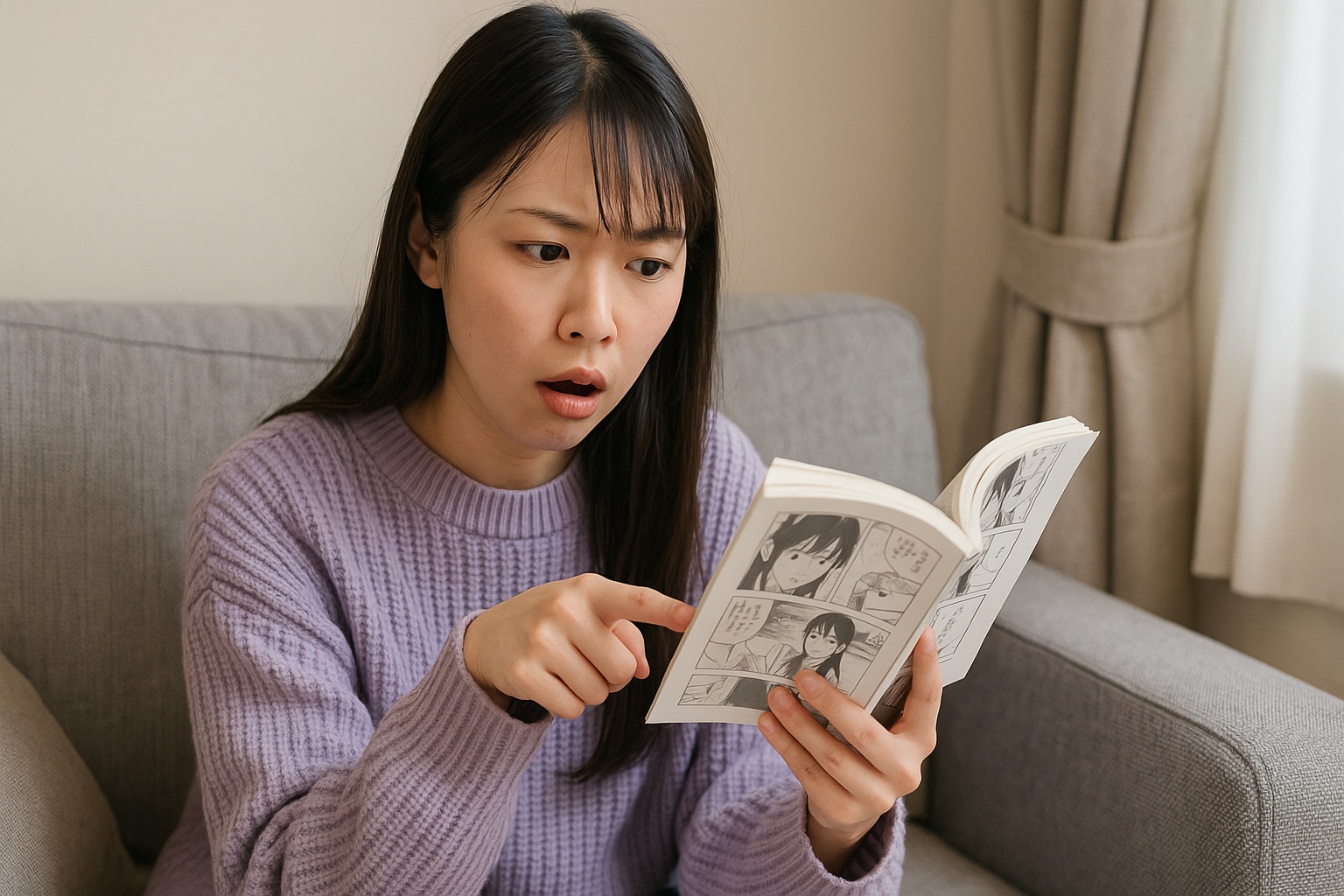
- 参考書日本史の選び方 ― 迷わない基準とは
- おすすめの学習ルート ― 共通テスト・私大・MARCH対応
- タイプ別おすすめ参考書 ― 山川・講義本・問題集の使い分け
- レベル別ステップアップ戦略 ― 基礎〜難関大まで
1. 参考書日本史の選び方 ― 迷わない基準とは
「おすすめの日本史参考書は?」という質問はとても多いですが、答えはひとつではありません。理由はシンプルで「読む・理解する・アウトプットする」のどこに課題があるかで必要な参考書が変わるからです。「日本史参考書おすすめ」を調べる前に、自分がどこでつまずいているかを把握するのが最初のステップです。
| 選ぶポイント | 判断基準 |
|---|---|
| 量 | 続けられる厚さか |
| 形式 | 読む型/図解型/演習型 |
| 相性 | 読んで理解しやすいか |
Q. 日本史参考書を選ぶうえで最重要なのは?
- みんなが持っているか
- 自分が理解しやすいか
- とりあえず情報量が多いか
正解:2/相性が悪い参考書は続きません。
A「とりあえず山川で良い?」
B「基礎としては良いけど、背景を補える本も一冊ほしいね」
理解の土台を作ることが成功の鍵
結局のところ最も伸びる勉強法は「流れを理解→知識で固める」です。背景を無視して暗記だけ進めると、共通テストやMARCHの正誤問題で崩れます。まず「読む+わかる」本を軸にすることが大切です。

「暗記より先に“理解の骨組み”を作ると、得点が安定します♪」
参考書の役割を分けて考える
参考書は“全部を網羅しようとすると失敗”します。役割は大きく分けて以下の3つです。
①読む(通史)②覚える(一問一答)③解く(問題集)
この3つが揃えば、独学でも十分戦えます。

「まず“読む参考書”を決めてから他を揃えましょう♪」
2. おすすめの学習ルート ― 共通テスト・私大・MARCH対応
日本史は「順番」を間違えると伸びません。まず通史→演習という流れを守りましょう。とくに共通テストでは資料・横断的理解が必要。一方私大では単語・正誤・テーマ史など、問われ方が異なります。だからこそ“共通の土台+進路別強化”が重要なのです。
おすすめの関連記事:システム英単語の効果的な使い方と学習戦略|Basic・中学版・音声・アプリ活用まで完全解説
- 共通テスト:通史 → 資料 → センター型問題 → 共テ形式演習
- 私大:通史 → 一問一答 → 私大特化問題集
- MARCH:講義本 → 資料理解 → 演習セット
- 逆算型:過去問→穴埋め参考書→通史確認
Q. MARCH志望で落としがちな視点は?
- 単語を覚える量
- 背景と流れを説明できるか
- 資料を見るクセをつけること
正解:2/「正誤問題で落ちる」の典型です。
A「共通テストしか受けないときは?」
B「資料+流れ理解があれば、一問一答は後回しでも大丈夫!」
共通テスト向けの注意点
共通テストでは、資料やグラフ・年表の“意味”を読み取れるかが得点差になります。用語暗記だけでは対応できません。まず通史を読んで背景を掴み、資料問題で「見方」を覚えると一気に得点が安定します。

「資料が“覚えるもの”から“読めるもの”に変わった瞬間に点が伸びます♪」
私大向けの参考書選び
日本史問題集おすすめとしては、私大対応型が必須。特に上智・早慶・MARCHでは正誤判定・テーマ史・資料論述まで広く問われます。覚えるだけでなく「なぜそれが正解か」を説明できる教材が有効です。

「“覚えている知識”と“使える知識”は別物なんです♪」
3. タイプ別おすすめ参考書 ― 山川・講義本・問題集の使い分け
参考書日本史は種類が多く、「どれも良さそう」に見えてしまうのが最大の罠です。たとえば山川は最強の基礎資料ですが、初学者には難しい面もあります。そのため「山川+講義本」の組み合わせが最も安定します。問題集も「共通テスト型」「私大型」「テーマ史強化」など目的別に選ぶことが必要です。
| 分類 | 特徴 |
|---|---|
| 山川系通史 | 日本史の地図として最適 |
| 講義本 | 流れと理由がわかる |
| 一問一答 | 知識を穴埋めする |
| 資料集 | 共通テストで必須 |
Q. 山川だけでは厳しくなる理由は?
- 量が少なすぎる
- 流れや因果が説明されにくい
- 図や資料がないため
正解:2
A「問題集だけでいける?」
B「基礎理解がないと“当たるか外れるか”の運ゲーになるよ」
山川を軸にした戦い方
山川は「通史の辞書」としては最高。問題は読む順番と補強です。先に講義本で流れを掴み、山川で整理→一問一答で締めると、最速で知識が体系化されます。山川は“いきなり読む本”ではなく“理解を確定する本”なんです。

「山川は“理解済みの人”が読むと最強になります♪」
問題集は“点を落とさない”ために回す
日本史問題集おすすめは「正誤問題」「資料問題」に強い構成が理想。とくにMARCH志望なら“歴史の因果”を問われる問題をやり込むことが必須です。ただし問題集は「完璧にする」より「失点を潰す」意識で回すと効率が倍増します。

「丸暗記型の演習より、“なぜ間違えたか”の分析が伸びを加速します♪」
4. レベル別ステップアップ戦略 ― 基礎〜難関大まで
参考書日本史の正しい使い方は「段階学習」です。基礎レベルから最難関まで、使う参考書と勉強法は変わります。いきなり難関向けの問題集をやっても得点に結びつかず、逆に基礎がないまま焦ってしまうこともあります。まずは、自分の現在の立ち位置を知りましょう。
- 基礎:講義系+薄い通史本(読む中心)
- 標準:山川+一問一答(固める段階)
- 難関:資料→正誤→テーマ史(分析中心)
- 最難関:横断整理+論述(総合処理力)
Q. レベル別に参考書を分ける理由は?
- 本棚を整理するため
- 必要な範囲だけ選択し学習効率を上げるため
- 全部やると疲れるから
正解:2
A「早稲田志望だけど今は共テ6割…」
B「まず“流れ理解+基礎定着”→それから難関対策で十分間に合うよ」
遠回りに見えて最短になる勉強法
とても重要なことですが、“基礎→標準→応用→難関”の順番は裏切りません。逆に「全部やろう」「最初から難問を完璧にしよう」とする人ほど失敗します。参考書日本史は「順番がすべて」と言っても過言ではないのです。

「やることを絞り、順番を守る人がいちばん伸びていきますよ♪」
学習を成功させる“流れ”を意識しよう
参考書日本史の本質は、“覚えた知識を線で結び、答案に変える”ことです。流れ→背景→資料→演習という流れが作れれば、どの大学でも戦えます。逆に言えば、この流れを意識しない限り、覚えたことは試験で使えません。

「“知識を動かせる”ようになった瞬間、急に点は伸びますよ♪」

「最初から完璧を狙うより、“まず軸を決める”ことが合格への近道です♪」